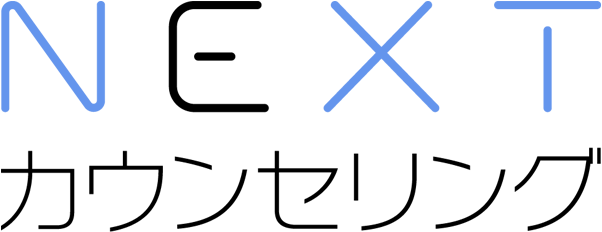子どもの頃、火の扱いや電気の危険を知らずにヒヤッとした経験がある方もいるかもしれません。私自身、幼少期にコンセントへ金属を差し込んでしまい、火花が飛んだことがありました。すぐに手を放したため大事には至りませんでしたが、ほんの一瞬の無知が命取りになるのだと実感した出来事でした。
パニック発作を目撃したときも、それに似た側面があります。知識がないまま関わると、相手を追い詰めてしまったり、逆に怖がらせてしまうこともあります。ですが、正しい理解と行動を知っていれば、支援者として大きな力になれるのです。
本記事では、「目撃者」「家族」「友人」として実際にどんな対応ができるのかを整理し、支援マニュアルとしてまとめていきます。
パニック発作とは
パニック発作とは、突然に生じる強い不安や恐怖の発作です。動悸、息苦しさ、めまい、発汗、震えなどの身体症状が一気に現れ、本人は「死んでしまうのではないか」という強烈な恐怖にさらされます。
重要なのは、見た目の激しさに比べて身体的には命の危険が少ないという点です。つまり、支援者は冷静さを保つことが第一歩になります。
支援者がとるべき行動の流れ
1. 安全の確保
まず、周囲に危険がないか確認します。車道や階段、混雑した場所などは二次被害を招きかねません。可能であれば、人混みを避けた場所に誘導します。
2. 「そばにいる」と伝える
発作を起こしている本人は「ひとりで苦しむ恐怖」に襲われています。
「ここにいるから大丈夫」「一緒にいるよ」と、短く安心感を与える言葉が効果的です。
一方で「落ち着いて」「大げさだよ」などは、さらに不安を高めてしまうため避けましょう。
3. 呼吸のペースを示す
多くの発作で「過呼吸」が起きます。無理に「深呼吸して」と指示するのではなく、支援者がゆっくり呼吸して見せることが効果的です。
「吸って…吐いて…」と声を合わせるのもサポートになります。
4. 水や姿勢を整える
- コップ1杯の水を差し出す
- 椅子や壁に寄りかからせて体を安定させる
こうした小さな配慮が、安心感を生みます。
5. 発作が落ち着いた後の対応
発作は通常10〜30分以内に収まります。落ち着いた後は「何かしてほしいことはある?」と本人に確認を。
必要以上に介入せず、本人のペースを尊重することが重要です。
支援の落とし穴
発作を見た支援者の多くは「何とか止めなければ」と思いがちです。しかし、実際には「止める」よりも「寄り添う」方が有効です。
無理に励ます、叱咤する、心配を大げさに口にする――こうした関わりはかえって症状を悪化させます。
まとめ
本記事では、他人のパニック発作を目撃したときに支援者がとるべき行動を整理しました。
- 安全を確保する
- そばにいると伝える
- 呼吸を示して整える
- 水や姿勢で落ち着きを助ける
- 発作後は本人のペースを尊重する
知識があるだけで、もしもの場面で落ち着いて対応できます。
共有のお願い
この記事はご家族や同僚、友人の間でシェアしていただければ幸いです。正しい知識が広まることが、当事者を救う大きな力になります。