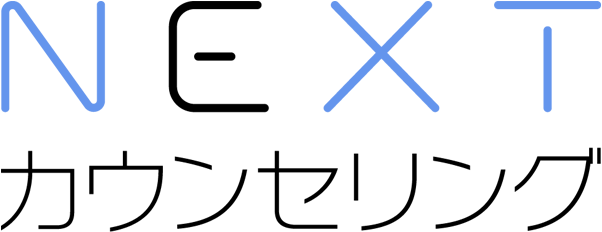「Medical News Today」月に8500万ものアクセス数を誇るメンタルヘルス・ケア系のサイトです。前回に引き続き、ここで紹介されていた、パニック発作を対処する方法についてご紹介し、解説をしていきたいと思います。
オリジナルのサイトはこちら→https://www.medicalnewstoday.com/about
本記事では、13の対処法うち、残りの半分の方法を簡単に紹介したいと思います。パニック発作への対処のゴールはコントロール感を取り戻すことです。コントロール感を取り戻せれば、その後は徐々に嫌な症状も軽減していくことになります。それぞれの紹介の後に、私の解説を加えていきたいと思いますが、まず最初にパニック発作とはどんな体験であるのかをおさらいします。
目次
パニック発作とは?
パニック発作は、突然に生じる、または予期されて生じる、身体の興奮と恐怖感を伴う体験です。突然に生じると言うのは、何がきっかけかわからない中で生じると言う意味で、予期されて生じると言うのは、きっかけが明確にわかっていて生じると言う意味です。
症状としては、身体(浅く早い呼吸、胸の違和感や痛み、心拍や血圧の増加、発汗、震え、めまいなど)症状と感情(心配や恐怖など)症状、そして思考(今何ができるか、あれが起きるかもしれない、死ぬかも、狂うかもしれないなど)症状があります。多くの場合、10〜20分で自然に治っていくものですが、1時間以上持続する場合もあります。
パニック発作は、誰にでも起る可能性のある現象です。パニック発作を起こすと、それが恐怖に感じられるので、それを恐れ(予期不安)特定の行動をしなくなる(回避行動)が伴う場合があります。これが続くとパニック障害と言われる状態になります。そしてその回避行動が顕著になり、外に出ること自体を警戒し始め、外に出なくなるという広場恐怖症を伴うこともあります。
では、以下でパニック発作を止める13の方法のうちの7〜13を紹介します。

7 マントラを唱える
マントラと聞くと、宗教的な意味合いを感じる方もいるかもしれません。ここで定義するマントラは「単語」(例:大丈夫)「フレーズ」(例:発作はすぐ終わる)「音」(例:あ〜あ〜)を意味します。もちろん、宗教的な意味合いを含む言葉、フレーズ、音でも良いです。それらマントラを心の中で繰り返すことによって、そこへの集中を高めることがこの方法の目的です。これにより、注意が徐々に発作からそれ、自然な回復が早まります。
解説:とてもシンプルで誰でも簡単にできる、思いつく、あるいは自然にやっていることかと思います。クライアントさんたちは、自然に「大丈夫だよ」と、あるいは「怖いね、でもすぐ終わるよ」と自分に何度も言い聞かせると言うことをやっている方も多いです。上記にあるように、目的は、発作に向く注意を逸らし、客観的に物事が見られるようになることで、コントロール感を取り戻すことにあります。十分な回数と時間をかけて行う必要があります。
8 歩いたり軽い運動をする
適度な運動は、呼吸のリズムを整え、そしてエンドルフィンというホルモン分泌によるリラクゼーション効果が期待できます。発作時の対処としても効果がありますが、日々の習慣として運動を取り入れると、ストレス値が減るので、発作が起きにくくなるという予防的な効果もあります。
解説:運動は、予防的な側面が大きいでしょう。発作を起こすということも、身体機能の習慣であるので、別の習慣を取り入れることで、発作も起きにくくなります。クライアントさんの中には、運動をすると、ドキドキしてくるので、それがパニック時の体の興奮と類似しており、怖さを感じる、という方もいます。その場合は程度を調整することが役立つでしょう。耐えられる程度なら、その身体感覚が怖いものではない、という学習にもつながり、結果的に発作を起きにくくする作用もあります。
9 筋弛緩法を行う
筋弛緩法は、リラクゼーションを促す方法です。筋肉の緊張と弛緩を繰り返すことで得られる開放感を味わい、身体から落ち着けていく方法です。様々な方法がありますが、発作時には思い出せなかったり、焦りがあるため、簡易的なものを実施するのが良いでしょう。身体のどこでも良いですが(腕やお腹が良いかと思います)に力を込め(5〜10秒間)ゆっくりと力を抜きます(20〜30秒間)。力を抜く過程で生じる開放感を十分に感じることで、パニックの身体症状や感情症状、そして思考の症状の軽減が期待できます。
解説:認知行動療法からのテクニックです。発作時には、体のいたる部分で力が入っています。そこにあえて意図的にさらに力を加え、緩めていくという行為を繰り返すことで①解放されたという心理的な意味合い②筋肉が弛緩するという身体的な意味合い③発作から注意を移すという意味合い、などで症状の軽減が期待できるでしょう。10回ほど繰り返せば、コントロール感は取り戻してける方法と考えて良いでしょう。普段から練習をしておくとなお効果は高く出ます。
10 気分が良くなるような「ハッピープレイス」(場所)を浮かべる
概念を使って発作を止めていく方法です。気持ちが落ち着く、安らぐ、安全でリラックスできる場所を思い浮かべます。場所から少し発展して、人の顔などでも良いでしょう。発作が起き始めたと思ったら、目を瞑り、場所に集中します。
解説:向き不向きがありますが、概念を扱うことが得意な方には効果があるでしょう。注意点として3つあります。1つ目が、発作が起き始めた始めるという点です。これはコントロール感が残っている時点を指します。概念を使うには、コントロール感が必要です。次に、発作時は頭を使いにくくなるということです。タイミング(起き始めた時点)を過ぎると「そんなことしている暇などない」となります。命に関わると感じ、焦りますから、持続して概念に注意を向けることが難しくなります。そして最後に、向き不向きがあります。概念を使うことがあまり得意でない人は、頭よりも体の実体験(例えば5感の体験)の方がはっきりと感じられるし、注意も維持しやすいでしょう。
11 処方薬(頓服)を服用する
手軽で、かつ、効果を予期しやすいのが、頓服を服用するという方法です。医師の診察と処方が必要になりますが、必要に応じて精神科や心療内科を受診し、そこで処方してもらうと良いでしょう。使用の仕方も医師から説明されますので、使用方法を守った上で使うと効果的です。
解説:パニックに悩む多くのクライアントさんが、医療機関を受診します。そして多くの場合、薬を処方してもらい、そして頓服と呼ばれる「必要に応じて使用する」薬を持つことになります。これらの薬は、即効性があり30分以内に、身体の機能を変え、心身の鎮静を促していきます。実際に使わずとも、多くの方が「お守り」として、処方薬を携帯しています。何かがあったときでも大丈夫と思え、安心感が高まるようです。
12 他人の援助を求める
発作が起きたその場面でも、発作を起こしながらも生活を続けている場合の場面(例えば職場)でも、一人で抱え込まずに人を巻き込むことは、効果的な方法です。知らない人ばかりの場面であっても「パニックが起きています。手助けしてもらえますか?」と伝えることで、多くの人は、しばらくはそばにいてくれるでしょう。また職場では、いわゆる「カミングアウト」をすることで、業務量や業種、あるいは勤務時間の配慮などもしてくれる場合も少なくないでしょう。
解説:人に敏感な日本では、欧米人が考えるように、容易に他人の援助を得られるとは感じにくいのが日本人です。それであっても、例えば電車の中で発作を起こした方が、その場で座り込んでしまったのを見て、席を譲ってくれたり、一緒に次の駅で降りてベンチに座らせてくれたり、というのを目撃したことがあります。また職場でのカミングアウトは、概してポジティブな結果になっているという話を聞きます。
発作を克服した人が口を揃えていうのが「発作になってよかった」です。苦しいけれども、過ぎ去ってみると学ぶべきものがたくさんあったという感覚なのでしょう。学ぶことの一つに、人のイメージが変わるということです。人は思っていたより、怖いものでも、冷たいものでも、無関心なものではなく、苦しみを抱える人には寄り添い手助けをしてくれる存在である、とパニックが治るプロセスを通じて学びとることができます。これは人生をより豊かなものにしてくれます。
13 発作のトリガーを学ぶ
発作は突然起きる場合があります。多くの場合、最初はこちらの形で起きるでしょう。どうして起きたのか、何が原因となっているのか分からないと、不安はつきません。いつ起きるか分からないからです。しかし、発作には必ず原因があります。それに気がついていない場合、それに気がつくことは不安を減らすことに役立ちます。例えば、人混みの状況にいる時、閉鎖された空間にいる時、お金の問題を感じた時、人前で話をする時、人と口論をする時、などです。トリガーが分かれば、解決に向けてより生産的に動くことができます。
解説:発作は、環境的なトリガーと内的な体験のトリガーが合わさって生じます。最初はどちらも分からないいことが多いですが、まずは環境的なトリガーを見出していくことが先決です。そして、その中で内的な体験のトリガー(特定の身体感覚、感情、思考)を見出していくと、自分でパニックを乗り越えていくことも可能です。内的な体験のトリガーに関しては、客観的な意見が役立ちますので、ここで専門家の手助けを借りるのも良いと思います。
まとめ
本記事をまとめます。本記事では、欧米の有名サイトからパニックを止める方法の7〜13までをご紹介しました。全ての方法に共通することは、コントロール感を取り戻すことをゴールとすることです。それを目的とし、言葉を唱えたり(7)、運動習慣で予防したり(8)や筋肉の感覚に働きかけたり(9)、概念を使ったり(10)薬や他人の力をかりたり(11と12)、また自分の発作の仕組みについてより良く知る(13)をご紹介しました。ぜひ役立ててみてください。