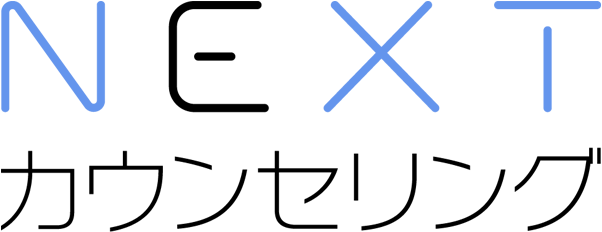「ちょっとした音で体が固まってしまう」「あの瞬間の映像が、今も鮮明に浮かぶ」――。
トラウマを体験した人は、出来事が過ぎ去った後も、心と体が当時の危険を覚えているかのように反応してしまうことがあります。
これは単なる「気の持ちよう」ではなく、脳や神経、そして身体全体のシステムが深く関わっている現象です。
脳科学から見たトラウマ反応
トラウマが脳に及ぼす影響を理解するうえで、重要な役割を果たすのが「扁桃体」「前頭前野」「海馬」という3つの領域です。
- 扁桃体(へんとうたい):危険を察知する警報装置のような働きをします。トラウマ体験をすると、扁桃体が過剰に反応し、些細な刺激にも「危険だ」と判断しやすくなります。
- 前頭前野:感情をコントロールし、状況を論理的に判断する領域です。しかし、強い恐怖やストレスの中ではこの部分の働きが低下し、「落ち着いて考える」ことが難しくなります。
- 海馬:出来事を時間の流れの中で整理し、「過去のこと」として記憶する役割を担います。トラウマ体験ではこの機能が乱れ、記憶が断片化し、フラッシュバックとして現在に蘇ることがあります。
このように、脳のネットワークが「危険はまだ終わっていない」と判断し続けることで、体や感情の過剰反応が続いてしまうのです。
自律神経系とトラウマ:過覚醒とフリーズ反応
トラウマは、自律神経系にも強く影響します。自律神経は、私たちの体を「戦うか逃げるか(交感神経)」と「休む・回復する(副交感神経)」の間でバランスさせる役割を持ちます。
トラウマを経験すると、このバランスが崩れやすくなります。
- 過覚醒(ハイパーアラウザル):心拍数が上がり、体が常に緊張状態に。眠りにくい、音や光に敏感になるなどの症状が見られます。
- フリーズ反応:危険から逃げられないと判断した脳は、「動かない」ことで身を守ろうとします。体が固まり、感情や感覚が麻痺するように感じることもあります。
どちらの反応も「生き延びるための防御反応」であり、意志の弱さではなく、体が自動的に選択したサバイバルモードなのです。
身体に現れるトラウマの影響
トラウマは「心の問題」と捉えられがちですが、実際には体のあちこちに影響が及びます。
- 睡眠:入眠困難や悪夢、夜中に目が覚めるなど、慢性的な睡眠の乱れが起きやすくなります。
- 消化:ストレスにより胃腸の動きが鈍くなり、食欲不振や腹痛が続くことがあります。
- 免疫:自律神経の不均衡により免疫機能が低下し、風邪や疲れやすさが増す場合もあります。
つまり、トラウマとは「心だけの問題」ではなく、心と体の両方に深く刻まれる体験なのです。
まとめ:体の反応は「生き延びた証」
トラウマ反応は、心が壊れてしまったサインではなく、体が「もう一度安全を取り戻すため」に必死で働いている証です。
恐怖やフラッシュバック、身体の緊張はすべて、あなたの脳と体がかつての危険から守ろうとしていた名残でもあります。
回復の第一歩は、「自分の体がいまも守ろうとしてくれている」と理解すること。
そこから少しずつ、安心を取り戻すプロセスが始まります。
参考文献
- van der Kolk, B. (2014). The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma.
- Porges, S. W. (2011). The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.).